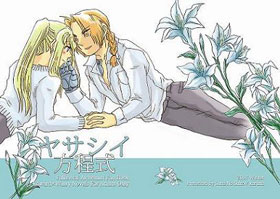
■鋼エドウィン NovelsOnly /¥1000
■仕様:A5版サイズ116頁(表紙込)/表紙フルカラー+マットPP
■本文:小説2段組/縦書き
■大人向。18歳未満の方の購入はご遠慮ください。
■表紙絵協力:さをりさん(SA-mode)
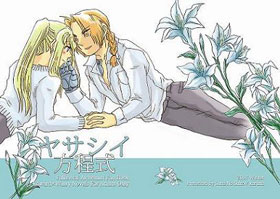
―――「どれほど近づいても2人は1にはなれない。
方程式は、ヤサシイようでやさしくない。
それでも、同じ夢は見れる。」
「こんなにも易しい方程式を、
難しくさせているのは、
あの二人が優しすぎるからだ。
ボクがいるせいで、
あの二人はやさしい感情に従えないのではないだろうか」
「アルが愚痴ってくれて、あたし嬉しい。
…だけど、ひとつだけ、大丈夫って言わせて」
「あたしね、エドのあの銀時計の中身を知っているの」
「お願い、エド…あたしに…優しく、しないで…」
「そのお願いは聞けねぇんだよ」
彼は切なげに呟いた。
「ア」と声をあげて、
ウィンリィは彼の腕の中でぶるっと身体を仰け反らせる。
「易しく、ないんだよ……バカ」
その低い声を落とすと同時に、彼はねじ込むように胎内に入ってきて、
ウィンリィは白い肢体を淫らにのけぞらせ、
髪を振り乱しながら、甘い声を上げる。
■本文サンプル■
「アンタの弟に言っといてくれ。国家錬金術師なんてロクでもねぇよって」
「そうだね」
相槌を打たれて、エドワードは苦笑いにも似た、自嘲に近い笑みをひとつ漏らしてカノトをちらりと流し見た。
軍の狗は嫌われているものだ。少なくとも国家錬金術師になって数年、エドワード自身、それを一番肌に感じている。嫌味も罵倒も慣れっこだった。しかし、カノトの言はそういった類のものではなかったらしい。苦笑いを一つ零して去ろうとするその国家錬金術師の背中に、カノトは試すように言葉を放った。
「あんないい人を待たせてるなんて、国家錬金術師はロクでもないっていうのは正しいかもしれない」
一瞬何を言われたか分からなかった。エドワードは、踏み出しかけていた足を思わず止める。
なにがだ、と呟きつつも、ふと胸を突いた予感は正しかったようだ。振り向いた先に、自分と同じ類の目をした男がいる。
「あなたはここに時々しか帰らないから知らないだろうけど」
来客のために開け放った玄関の扉に、身体半分を預けるように寄り掛かって、カノトはエドワードを精悍に見つめた。睨んだと言うほうが正しいかもしれない。
「あの人はずっとあんたしか見てないよ。あんたがメンテナンスの最中、彼女をずっと盗み見ているようにさ。頭にくるほど、あんたをずっと待ってる」
「……」
カノトを見据えるエドワードの眉根に皺がひとつ刻まれる。不愉快そうに顔色を変える国家錬金術師の視線を、カノトは静かな眼差しで受け止めた。
「一度聞いたことがあるんだ。ウィンリィさんに」
「…………何を」
「あんたのこと」
「……」
扉に寄り掛かったまま、カノトは軽く両腕を身体の前で組んだ。首をカクンと折り、斜めになった視界の下から覗き込むような目線で、エドワードの反応を観察する。
「幼なじみ、ってしか言われなかったけど、話してるうちに彼女がどう思ってるかなんてすぐに分かった。さっきいちいち聞かなくたって知ってたんだよ、俺。……そんでもって腹が立った」
「……」
シトシトと降りしきる雨足が重低音に響き渡り、玄関先に立つ二人の耳の裏を等しく静かにくすぐる。
カノトが何を言い出すのか、エドワードは静かな面持ちで待った。銀時計を失くしたことで焦っていた思考は緩やかに明瞭になっていき、目の前の男が、自分と似た感情に支配されている存在なのだと、ようやく実感を抱く。
「俺だったら一人にしないし」
「……」
「ずっと傍にいてあげる」
エドワードは押し黙って、カノトの声を聞いた。不思議と怒りは湧いてこなかった。心臓の音に呼応するように、身の内に跳ね上がる激情は、怒りの類ではなかった。それは確実だった。激情は哀愁となって、シトシトと降り続く雨の音に混ざりながら、エドワードの身体を侵食していく。
カノトはこれが最期だ、とばかりに言い放った。彼は、恋するがゆえに容赦がなかった。
「あんたが彼女こと、空気って言う資格はないよ」
降りしきる雨の音が、二人の沈黙を優しく覆うように響く。唇を一文字に引き結んで、エドワードはカノトを声もなく見据えていた。負けじと見返してくるカノトの眼差しの奥に、自分と同じものを想い描いていることを痛く察知する。それでも譲る気はなかった。
「言いたいことはそれだけか」
「……」
カノトに答えがないとわかると、エドワードは再び踵を返そうとする。
「言っとくけどな」
半分背中を向けながら、エドワードは睨むような眼差しでカノトを見据えて低く呟いた。
「あいつはただ待ってるだけの奴じゃねぇよ」
少し怪訝そうに眉をひそめるカノトを見やりながら、エドワードはなおも言葉を継いだ。
「一人にしないとか、傍にいてやるとか、そんな目でしかあいつを見てないんだとしたら、痛い目見るぜ」
言いながら、エドワードは痛烈に思い知らされている。何をしたってあいつは泣くのだ、と。カノトが言うことを、実際にウィンリィにしてやったとしても、彼女は泣くか怒るかしかしないだろう。ウィンリィは優しい。「あんたをサポートするって決めたから」と宣言してみせたその日から、ウィンリィは望んでそれをしていて、エドワードはそれを受け入れている。それがないと前には進めない、それほどに、ある意味、彼女に依存している。だから、仮に、カノトが言うような傍にいてやるだとか、一人にしないだとか、そういうことを彼女にしてやっても、ウィンリィ自身は喜ばない。むしろ怒るのだ。そして、泣く。弟と自分と、歩んできた道を誰よりも身近に知っている。弟の現実を知っていて、胸を痛めている。それゆえに、彼女はエドワードに対して、必要以上に望もうとしなかったのだ。前だけ見てと、まるで叱咤するように、後ろから自分を見ている。
だからカノトが言うような「してやる」では駄目だった。優しい彼女はきっとそれを拒否するだろう。そして、したくても「できない」ことのほうが、エドワードにはまだ多かった。
こんな形で思い知らされるとは。
エドワードはカノトをただ黙って見つめるしか出来なかった。カノトに対して怒りはなかった。腹立たしいのは自分に対してだった。
落ちた沈黙を先に切ったのはカノトだった。
「痛い目ならもう見た」
「……」
何の話か、一瞬エドワードは理解できなかった。カノトは視線を濡れた石畳に落としながら、自嘲的な笑みを唇の端に浮かべた。
エドワードは押し黙ったまま、カノトの言葉を振り切るように背を向けた。答えは分かりきっていた。……分かりきっていると瞬時に断言出来るほどにヤサシイ式なのに、どうしてもこうも難しく思えてしまうのだろう。
「彼女はアンタじゃないと駄目だってハッキリ言ったよ。空気でもいいのって言いながらさ」
パシャリと泥を跳ね飛ばしながら雨の中に飛び込む。赤いコートを翻しながら、昼間だというのに雨天のせいでどんよりと翳った通りに出ようとする。背中にカノトの声を聞きながら、エドワードの心には暗澹とした影が落ち始めていた。言われなくても一番自分が分かっていることだった。そんな自分に出来ないことをやれると断言したその男の声をこれ以上聞くのは苦痛でしかなかった。
(中略)
部屋の中は熱っぽい匂いに蒸せていた。ノックを一つ響かせて、エドワードは扉を押し開く。
ガーフィール工房の二階にはウィンリィの部屋があった。階段を昇って一本通りの廊下にあがると、その両側にそれぞれ部屋へ繋がる扉が並んでいる。そのうちの部屋一つを、エドワードは整備中の間、ガーフィールの厚意により借りていた。
トレイを片手に持ったまま、エドワードは後ろ手にドアを閉める。廊下から煌々と漏れた光はあっという間に遮断されて、視界は薄暗い闇に落ちる。
「誰…?」
か細い声が落ちた。
部屋に明りは無く、外は暗い。振り続ける雨足だけが、低くしめやかに駆ける。
「オレ」
一拍の間を置いて、「何」と訊いてくる声はびっくりするほど力弱い。それに気が殺がれながら、エドワードは努めて低く静かに答えた。
「おまえ、飯食ってねーだろ……アルとガーフィールさんが…様子、見て来いって」
そう、と小さく声がした。手狭に物が置かれた部屋は、エドワードが滞在の間に借りている部屋と同じ造りのはずなのに、対極的に生活感に満ちている。ラッシュバレーでの彼女の部屋だ。日常が溢れている。
奥の窓脇に据えられたベッドに、そろりと一歩踏み出した。乱れたシーツの下に彼女の肢体が形取られているのが薄闇の中でもよく見える。シーツの上に波打ちながら広がるのは彼女の長い髪だ。それを見て、不意に昨夜のことを思い出してしまい、エドワードは記憶を振り払おうとした。自己嫌悪にも似た苦いものが身体を駆け巡る。
うつしたのは兄さんだろ、というアルフォンスの声が響く。そう、うつしたのはエドワードだった。うつるかもしれない、と思いながら、彼女を抱いたのだ。久々に会って、自分の衝動を止められなかった。
本当は、朝からそれをずっと謝ろうと思っていたのだ。だが、先客がいて、叶わなかった。本能的に苦手だと思ったのは、あのカノトが、自分と同じ想いを彼女に抱いていると分かったからだ。そうしているうちに、素直に謝るタイミングを逃したまま、夜になってしまった。昼間、路上で彼女が泣いていたような気がする。それも気になっていた。「空気でもいい」と彼女が言ったその意図がよく分からなかった。なぜ彼女は、昼間あんなにも頑なだったのだろう。彼女が怒っている気がした。そして、それは自分のせいだともなんとなく分かった。
ことんと落ちる沈黙を切るように、エドワードは搾り出すように低い声で呟いた。
「ごめん」
二人きりになって、やっと口に出たのは謝罪の言葉だ。朝からずっと抱えていたもやもやだ。それをようやく一日かけて、今吐き出した。
しかし、彼女の反応は無い。
「だ、だけどな」
反応がない彼女に不安になった。彼女が横たわるベッドに近づく。ベッド脇に置かれた小さな読書灯の横に、食事の載ったトレイを静かに置きながら、彼女が無反応なことに焦りを覚えた。
「けど、お前だって悪いぜ。あんな……ことで風邪がうつるとか、オレ、本気にしてなかったし…………」
言いながらも、言い訳だろ、とエドワードは内心焦る。こんなことを言いたいわけではないのに。
いいよ、とようやく彼女は小さく答えた。
「……アンタが、責任とれって言うからよ」
ぽそっと呟いた彼女の言葉に、少しだけ棘がある。
「アンタのワガママに、付き合ったのよ」
その言い方に、思わずエドワードはむっとする。自分が怒るのは筋違いだったが、エドワードは自分が何を言いたいのか、何をしたかったのか、徐々に分からなくなっていた。彼女のことになると、思考は論理的に結論をはじき出さない。だから戸惑う。全部が終わってから「しまった」と思うこともある。例えば昨夜のことだってそうだった。
背を向けたまま横たわる彼女は金髪をほどいていて、流れる髪の合間からのぞく肩のラインを睨みながら、エドワードは口を開いた。
「あの時、オレもちょっとおかしくて…それで責任とれとか言ったけど、……冗談だったし、元はといえばお前の頼みもちょっとは原因あると思ったからで……」
だいたいなぁ、とオレは続けた。
「嫌なら嫌ってハッキリ言えばいいだけだろ。責任とれって言ったのは確かだけど、おまえはうつせって言ったし」
(ハッキリ言え、ですって?)
彼の言葉を背中に聴きながら、ウィンリィはぎゅっとシーツの端を握り締めた。エドワードは何を言っているのだろう。ズルイ、とウィンリィは唇を噛んだ。
エドワードは暗がりの中で、反応の無いウィンリィを軽く見据えた。しかし、言葉は待っていても、与えられない。
「……」
なんで自分の口はこうも止まらないんだろう、とエドワードは腹が立ってくる。ウィンリィのせいにしたいわけではないのに。言いたいことはそういうことではないのに。本当はもっと別のことを言いたかった。
しかし頭を巡るのは昼間のカノトの声だ。彼女のことをどう想っている? 素直に好きだと言えるわけがなかった。アルフォンスの前だったのだ。そしてなによりも、そんなことを聞くような男が、彼女の傍にいることに驚いた。怖くなった。
違う、言いたいのはそうではなくて、と頭をめぐらせているうちに、彼女がどこか怒ったように呟く。「もう、聞きたくない」と。
怒らせるのは当然かもしれない、とエドワードは思い直す。しかし、納得がいかなかった。こうではないのだ、もっと言いたいことがあったのに、何だっただろう。
しかし、そうこうしているうちに、「もう、出てって」とウィンリィはハッキリとした口調で言った。もう、聞きたくない、と。
「だいたい……」
横たわったまま、ウィンリィは聞こえるか聞こえないかの小さな声で低く呟いた。
「……今日出発するって、……言ったくせ、に」
(なんでアンタはここにいるのよ?)
ウィンリィは腹立たしかった。これでは何のために仕事を急いだか分からない。風邪を引いた自分が情けなかった。意図した結果ではないにしろ、エドワードとアルフォンスはまだラッシュバレーにいる。まるで風邪をひいた自分が引きとめてしまったように思えて、ウィンリィは腹立たしかった。
「もう、出てって」
ウィンリィはもう一度呟いた。一人になって、一人で眠りに落ちたかった。朝になればまた新しい一日が始まる。この夜が何事もなく過ぎれば、全て解決するように思えた。
「……」
そこに頑なな拒絶があることを悟って、エドワードは言葉を失う。売り言葉に買い言葉だった。背中を向けたままの彼女を暗がりの下で見据えた。整備室では見慣れた背中があった。しかしどこか華奢で力弱い、いつもとは違う背中に見えた。
触りたい、とエドワードは思ったが、唇は思考と喧嘩して、別の言葉を紡いだ。
「……わかった」
これ以上は何も言ってはいけないとエドワードは己に言い聞かせようとした。墓穴を掘るだけのような気がする。しかも相手は病人だ。
「……飯、少しは食ったほうがいいぜ」
それだけを言い残して、エドワードは踵を返す。後ろ髪をひかれるような気分だったが、これ以上はどうしようもない気がした。彼女をまた怒らせてしまった気がする。腕を壊しては彼女を怒らせ、二人っきりになってもうまいことを言えない。伝えたいことはあるのに、言葉はいつもうまく出てこなかった。
頭を冷やそうと思いながら、エドワードは歩を進める。しかし、か細い声に呼び止められた。
「待って」
進みかけた歩が止まる。エドワードは一瞬、全身の挙動の全てを止めた後、ゆっくりと一つ息を吐いた。
「……なんだよ」
努めて静かに声を返そうと思った。部屋に響き渡る雨の音のように、ひたすら波の無い静かな声で。
言いたいことがあるけれど、言わない。お互いに、それは同じ。分かってるけれど、知らんぷりしてる。でもいつも期待してしまう。そして、期待は期待のまま、終わらせてしまっている。それでいいし、それでなんとか今までなってきた。言葉なんか必要なかった。身体を重ねていれば、それで伝わると思っていた。だけれど、何か足りない、とエドワードは思っていた。例えば、今この瞬間。何を言えばいいのか、自分は何かを言いたかったはずなのに、それすら思い出せない。言葉に出来ない。なぜこうも難しいのだろう。
かぼそい声が、決定付けるように呟いた。
「……そばに、いて」
かそけくような、本当に擦れた小さな声で、彼女はそういった。
「……え?」
驚いて、エドワードは弾かれたように振り向く。
背中を向けていたはずの彼女が、横たわったまま自分を見ていた。正面から見つめあう。ぬるく澱んだ空気の中を、視線二つがひたりと重なる感覚に、エドワードは眩暈を覚えた。不意にせりあがる心臓の音は、喜びのせいだと分かって、ひどく狼狽した。
そんなことを言われるのは初めてだった。
ベッドに横たわったまま、彼女がみあげてくる。潤んだ瞳がエドワードを真っ直ぐに射ていた。
「傍にいて。……お願い」
ドアノブに掛けていた手を離す。ドアの向こうから零れた廊下の光は、問答無用で掻き消える。踵を返し、彼女の元へと足を向けた。
それに弱い、とエドワードはひとりごちた。
彼女のお願いに、……彼女に、弱いと。
(中略)
雨の音がやさしい。
降りしきる雨脚は部屋の中にひそやかに響いていた。そして、その音に重なるのは、二人分の乱れた呼吸。
ウィンリィはエドワードの顔をまともに真正面から見ることが出来なかった。それでも逃れることは出来ない。身体はまだぴったりと繋がったままで、彼の膝の上に抱えられるようにして向かい合って座っている。触れた肌はどこもかしこも痛いほどに熱い。
言いながら既に後悔していた。だから、ウィンリィは顔を上げられなかった。エドワードの顔を見るのが怖い。こんなに密着して、息遣いが降りかかるくらいに抱き合っていて、それでも顔を見ることが怖い。傍にいることが怖い。傍にいてと言ったことが怖い。
沈黙が鉛のように重く落ちた。ただ聴こえるのは雨の音と、すぐ間近の彼の息遣いだ。時間の流れが途方もなく遅く感じられた。彼は黙っている。何も言わない。ハッキリ言えと言ったのは彼のほうだ。だから、ウィンリィは言ってしまった。
彼が頬に触れてきた手に手を重ねたまま、ウィンリィはエドワードの首元を見つめていた。顔をあげられないのは、不安でたまらないからだ。身体だけではないものを、離されそうで怖かった。
「な、に……」
不意に、擦れた声が落ちる。なに言ってるんだ、と言いかけたエドワードは、途中でまた言葉を失う。
俯いたまま決して自分のほうを見ようとしなくなった彼女の顔を覗き込もうとした。しかし彼女は決して自分を見ようとしない。何かに怯えているように、ふるふると瞳を揺らせながら虚空を見つめている。言われた言葉はあまりに易しい単語なのになぜか理解が追いつかずに、エドワードは呆けたように目を丸くしていた。
わざわざ、言うことか?
そう思ったが、エドワードはすぐさまに、「いや違う」と思考を打ち消した。面と向かってそんなことを言われたのは初めてだった。
お互いにそういうことは言わないようにしているのだと、無意識にどこか避けているのだと、そう思っていた。言う必要などないと思っていた。緩やかにその言葉を咀嚼して、分解して、再構築していく。まるで錬金術のように、与えられたその感情から、自分の感情が再構成されていく。
……ゆるゆると襲ってくるこの感情は。
「あ……」
エドワードは思わず彼女の頬から手を離す。そして、離したその手で、自分の口元を覆うようにして隠した。
半ば強引に手を離されて、ウィンリィの手もハタリと落ちた。ウィンリィはやっぱり、と失望した。思わず顔をあげる。やはり言わなければよかったのだ。言って、と言われても言わないほうがよかった。今まで絶対に言わなかったのに、どうして言ってしまったのだろう。彼の行為に全てを委ねるように、身体も心も開いて、熱に犯されて、言ってしまったのだ。かなわないのだ。
「今の、なし……」
「……」
ウィンリィは気が付いたら口走っていた。瞳に焦った色を隠さないまま、エドワードに希った。
「やっぱり、忘れて……っ」
顔をあげてエドワードにすがれば、彼は口元を手で覆ったまま視線をそらす。
「エド…?」
様子が変だ。
心臓がさらに重く鉛を抱えたように沈むのをウィンリィは自覚する。怖かった。「わすれて」ともう一度言いかけたとき、ようやく「無理」というくぐもった声が返される。
エドワードは涙目のまま自分を見返してくるウィンリィに、やっとのことで視線を重ねることが出来た。自分の頬が、焼けたように熱くなっているのを自覚している。口元を隠すようにして覆った手を下げることが出来ないのは、見られたら困るからだ。
どうしようもなく、緩んでしまう口元を。
エドワードの反応がいまひとつ分からず、ウィンリィの不安は増大していく。「無理」と口を隠しながら答えたエドワードの顔は、耳まで茹でたように赤い。不安げに揺れるウィンリィの青い目を見やってから、エドワードは「無理だ」と改めて言葉を返す。そして、自分の口元を覆ったまま、彼女の目を見ながら確認するように、「言いたいことって、それ?」とゆっくりと尋ねた。
目の前の青く大きな瞳が、困ったように迷いながら、頷くように瞬く。
「………それ、オレが、困ること?」
なおも問えば、ウィンリィはさらに困ったように目を潤ませてエドワードの視線から逃れるように目線を脇に逸らす。そんなウィンリィを見つめてから、エドワードは不意に目を閉じる。大きく震えるようにひとつだけ息を落とした。それから、唐突に自分の口元を覆っていた手の平を返すようにしてウィンリィの顎を捉える。
「あ」
ウィンリィの唇から小さく声が零れたが、エドワードはお構いなしに彼女の唇を激しく貪り始めた。キスを続けながら、ウィンリィの身体を再びシーツの上に押し倒す。唇を食まれ、舌を絡めとられるように激しくキスが落ちてくる。息が続かない、とウィンリィが新しく涙を滲ませたところでようやく唇は解放される。
「……まっ……て…」
彼が行為の続きをしようとしていることに気づいて、ウィンリィは抗うようにエドワードの身体の下で身をよじった。
「や、だ」
エドワードは何も言おうとしない。怒っているのか何なのか、はっきりして欲しかった。自分は言ったのだ。言えと言われたから、だから言った。エドワードの事情は痛いほど知っている。自分の言葉が何かを変えるわけでもない。メンテナンスが終われば、エドワードは目的のためにまた自分の前から去るのだから。それでも、答えが欲しい。明確な答えが。このまま行為に流されて、うやむやにされたくない。
あたしは、言ったんだから。言ってしまったんだから。
「やっぱり、怒ってるんでしょ……!」
噛み付くようにして自分の首筋に唇を這わせてくるエドワードの身体を押しのけようと躍起になりながら、しかし身体に力が入らないのを悔しく思いながら、ウィンリィは声を上げる。誤魔化されたくない。ここまで言ってしまったからには。
肌をさすような快感がざわざわと蘇ってくる。自分の肌を這う彼の唇の感覚に流されまいと、ウィンリィは意識を必死で手繰る。怒るなら怒ればいい。困るならはっきり言えばいい。……どんなに誤魔化そうとしたって、これが本心なのだ。頭では理解していても、感情のところで首を縦に振れない、誤魔化せない。だからどうしようもなくワガママなんだと。
ウィンリィはそれを自覚して情けなくなってくる。自己嫌悪だけが残っていた。誤魔化そうとすればするほど、目の前の彼がすきなのだと、自覚させられる。…はっきり困ると言えばいい。誤魔化さずに言ったんだから、エドワードもはっきり言えばいい。
「言ったから…だから、もう…」
「…やめない」
ウィンリィは目を丸くする。
エドワードは、やめねぇ、ともう一度吐き捨てるように低く言う。
「あ…」
ウィンリィはエドワードの身体の下でぶるっと身体をひとつ震えさせる。エドワードがさらに身体を沈めたからだ。繋いだ肉茎がめり込むようにウィンリィの奥を突いて来て、不意に立ち昇る快感にぞわりと身体が反応した。
「や……ぁっ…」
「言った」らこの行為をやめると言った癖に。エドワードが分からなかった。
「誤魔化さ、ないで…っ」
身体の真ん中から、生ぬるい快感が波のようにじわじわと押し寄せ始める。それに気をとられないように必死になりながら、ウィンリィは涙声でエドワードに抵抗する。
「誤魔化して、ない」
少しばかり切れ切れな彼の声が、しかししっかりとした口調で返ってくる。それを耳で聞き取りながら、ウィンリィは声を抑えようとするが止まらない。
「あ……、ぁ…ん…っ」
ウィンリィはのしかかってくる彼にしがみついた。何かを確かめるように緩やかだった彼の動きは、少しずつリズムが早くなっていく。それに伴うようにして、ウィンリィの声も短く切れ切れに漏れていく。
「ず、るい……っ…」
「なに、が」
「やめるって、…言った癖に…ぃ…っ…」
それに対して、そっけない言葉が返ってきた。「オレ、ワガママだから」と。動きを止める様子も無く、エドワードは密着していた身体を少し離して、目の前で揺れる彼女の両の胸に唇を押し当てる。「ワガママだけじゃないわ、嘘つきよ」と反論する彼女の声は、途中から艶めいた喘ぎに変わる。
彼女の胎内をグチグチと掻き混ぜるように動きながら、エドワードはどうしようもない感情に自分が支配されていくのを覚えている。は、と息を短く落としながら、エドワードは喘ぎを漏らすウィンリィの唇を塞ぐ。涙を滲ませながら唇に応える彼女を感じるだけで衝動はどんどん膨れていく。
……ゆるゆると襲ってくるこの感情に、名前をつけるとしたら何がいい。
彼女に言葉を返すようにして、好きというのはあまりに簡単すぎた。いまさら、だ。傍にいて、と彼女がハッキリ言った。…傍にいたい。これは、誤魔化しようがなく本当の気持ちだった。彼女の望みをかなえてやりたくて、でもそれが出来ない今の自分がある。それでも彼女がそう望んでいると知って、かなえられないと分かっている自分はそれでもどうしようもなく嬉しいのだ。だから、自分はワガママなのだ。そして、だからこそ、まだ、言う資格は無い気がした。泣き喘ぐ彼女に、好きだと囁くのは恐らく簡単で、あまりにもそっけなく言えてしまう。だから、いまはまだ。
だが、彼女は、誤魔化さないで、という。誤魔化しているつもりは無いのだ。答えは出ている。お互いに同じことを願っている。
これほど、答えはヤサシイのに。
…続きは本文で。
![]()