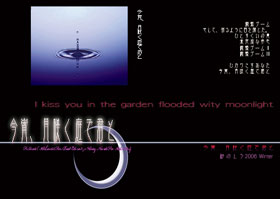
■鋼エドウィン NovelsOnly R18/¥1500/
■仕様:A5版サイズ200頁(表紙込)/表紙フルカラー+マットPP
■本文:小説2段組/縦書き
■大人向。18歳未満の方の購入はご遠慮ください。
■コピー誌6本加筆修正再録+新規書き下ろし2本
■本文中に挿絵5カット含みます。
■挿絵協力:羽曳 功さん(MINE)
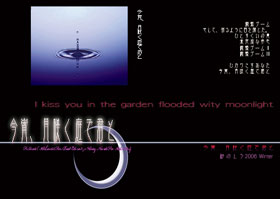
「おまえの顔見てると、……オレが負けそう」
「生きて。……絶対に死なないって、あたしに約束して。
あたしだけに」
「でもな、これに、救われている。この手に、生かされている。
だからな……おまえの手は、生かす手だ」
「教えてあげる、から、強く握って。……離さないで」
「おまえに忘れさせたいんじゃない。
……オレが、忘れたい、んだ」
「して。……エドので」
「好き、なんだ」
「エドって、ズルいね」
(あんたはあたしを振り返らない)
遠のく背中を見つめながら、
ウィンリィは言い聞かせるように何度も繰り架す。
だから、ひかりさすあなたを見つめながら、泣くのだ。
あなたがあたしを見てくれている夜の時間、
何も要らないと強がって
本当の意味では泣けなかった代わりに。
<書き下ろし「ひかりさすあなた」より>
■収録内容■
【コピー誌再録】…加筆修正済。6作。2005年08月から2006年08月発行分。
・微熱ゲーム
・そして、祈るように目を閉じた。(→サンプル本文抜粋)
・ひとすくいの青
・未完成な赤色(→サンプル本文抜粋)
・微熱ゲーム2(→サンプル本文抜粋)
・微熱ゲーム3
【書き下ろし】…新規書き下ろし2作。約64ページ相当。
・ひかりさすあなた(→サンプル本文抜粋)
・今宵、月咲く庭で君と(→サンプル本文抜粋)
■本文サンプル■
*少々性描写を含んでる部分もありますので、
苦手な方はご注意ください。
1.「ひかりさすあなた」より抜粋
思い出したように、ウィンリィが控えめに身を離すのを、エドワードは抵抗なく受け入れる。 二人して無言だった。
心臓が何かを急かすように波打っていた。エドワードは呆然とする。
(ありゃなんだ……?)
目の前で見せられた事を咀嚼して、理解しようとする。そして、間が悪いというべきなのか、いわないべきなのか、目の前にはウィンリィがいる。
エドワードの手を逃れたウィンリィは顔を赤くしながらも、俯き加減に床を睨んでいた。視線の先に、棒のようにつっ立っている二人分の足がみえる。一歩分もない距離を跨いで、二人して身体を向き合わせている。
(心臓がうるさい)
ウィンリィはぎゅっと口の端を硬く結ぶようにして、足元を睨み付けた。せりあがる動悸に飲み込まれてしまいそうで、顔があげられない。何かを見透かされてしまいそうで、エドワードの顔を見ることが出来ない。それを嘲笑うかのように、ウィンリィの頭の中に蘇ったのは、ナタリアとの会話だった。
気がついたら、唇は、勝手に言葉を発していた。
「…………悪かったわね…あたし、なんか、で」
「え」
ぽかんとするエドワードをウィンリィは顔をあげて、睨み付けた。
「あたしなんかで、……悪かったわね!」
なんで、とエドワードは言いかけて、うまく声が出ずに言い直す。
「な、なんで怒るんだよ!」
「……知らない!」
ぷいっとそっぽを向いて、ウィンリィは背を向けようとする。しかし、意味わかんねぇ、と混乱するエドワードは、ウィンリィの動きを阻むように、手首を再度掴んだ。
「ちゃんと、説明し……」
しかし、掴まえたウィンリィの顔を見てとって、エドワードは声を失う。
切り込むように真っ直ぐに見つめてくる、静謐な蒼の眼差しがそこにある。
「してみる?」
(なにを言っているの?)
ウィンリィは慄くように心の中で誰にともなく問うていた。しかし、答えをくれるものは誰もいない。ウィンリィも、待つつもりはない。身体が、唇が、全てが、ウィンリィの預かり知らぬところで、答えを引き結んで身体に命令する。答えに伴う行動を命令する。ウィンリィは言いながらも、途方に暮れていた。
唇は勝手に、悪戯でも思いついたように囁いた。エドワードを真っ直ぐに見詰めたまま、彼の反応をウィンリィは待った。
エドワードは、感情の読み取れないウィンリィの静かな表情を見つめながら、なにが、と問う。しかし、問うた声は乾いていた。喉がカラカラに干上がっていた。どうしてだか分からなかったが、エドワードは一瞬にして、彼女に追い詰められた気分になったのだ。
(なんだ、その、顔)
エドワードは動揺していた。息を呑んで、彼女を見つめ返す。
知らない女が、そこにいる。
「してみる?」
答えは簡単だった。キスしてみる? と、まだ知らない唇が、あっさりと言ってのけた。
「なに、言って……」
干上がる喉が痛くて、エドワードは唾を呑む。しかし、それはあまり慰めにはならなかった。何かを欲するかのように、喉が渇いている。渇きを癒すものを探している。そして、思いつく。
二人きりの整備室で、頭を並べるように彼女と向かい合って立っていた。同じ高さの視線が、針と糸で縫いとめられたように動かせなかった。その視界の真ん中で、誘うように動いた小さな唇。
(きす?)
なんだっけ、と出てきた疑問に答えるように、頭に再生される、キスシーンがひとつ。思い出して、身体に緩やかに熱が立ち昇り始めた。
しかし、唇はさらに続きを謳う。
「嘘、よ」
は? とエドワードが目を丸くしていると、ウィンリィはくすっと笑った。どこか意地悪い笑みだった。
「本気にしたの?」
言ったじゃない、とウィンリィは笑った。
「誰が、アンタなんかと」
とん、と両手を彼の胸に軽くついて、ウィンリィは彼から身体を離す。
一瞬、泣き出すのではないか? と危ぶみたくなるような表情をウィンリィが見せたような気がしたのは錯覚だったのか。目の前で悪戯っぽい笑みをにっかり浮かべた彼女を見て、白く焼けていたエドワードの思考は緩やかに戻っていき、比例するように彼の頬には朱が立ち昇る。
「お、ま、え、……っ!」
べ、とウィンリィはエドワードの目の前で舌を出してさえ見せた。
「なぁに、考えてんのよ」
「………っ」
言葉を継げずにいるエドワードを尻目に、ウィンリィは彼に背を向け、肩にかけていたバンダナを頭に巻く。
「さぁって、仕事仕事!」
「おまえ……」
エドワードは羞恥で赤くなる頬を左手で押し隠そうとしながら、ぼそっと言った。
「おぼえてろよ……」
ウィンリィはくるりとエドワードのほうを振り向く。
「足、診て貰って。ばっちゃんに」
エドワードの言葉に、彼女は答えなかった。そこにあるのは、仕事を控えた職人の顔があるようだった。
「待合室にいないなら、外にいるかも。呼んできて」
「……」
エドワードは彼女の背中を一瞥すると、返事もせずにくるりと背を向ける。それを測ったかのように、ウィンリィは振り向いた。怒ったように無言で開けっ放しの扉へと足を差し向けるエドワードの背中がある。
(振り向かない)
あんたは、絶対に、あたしを振り向かない。
それは、いつもウィンリィの中にある、揺るぎない確信だった。
振り向かないその背中を、ウィンリィは見つめた。
「エド」
「……なんだよ」
呼んでくればいいんだろ、とエドワードは軽く左手をあげて分かったよという意思表示をする。彼女に背を向けていれば、顔を隠す必要もない。とにかく一刻も早く、この場から逃れたかった。
ウィンリィはちらりと床に視線を滑らせた。遠のいていく。半歩も無かった距離が、広がっていく。
「エド」
ウィンリィは再度名を呼んだ。呼びながら、足を踏み出している。広がってしまったその距離を、再度埋めるように、踏み込む。
なんだよ、と、名を二度呼ばれてようやく振り返ったエドワードは、ぎょっと目を丸くした。
振り返ったすぐ先に、ウィンリィの顔がある。
「な……」
エドワードの金色の瞳が、さらに丸く見開かれる。視界に翳がさして、目の前が彼女の青の眼差しで一杯になる。
顔を軽く傾けたウィンリィは、エドワードの頬に手を添えた。吐息が感じ取れるほどに顔を近づける。二人の足元の距離は、これ以上ないほどに埋められていた。
身をひこうとしたが、間に合わなかった。正確には、間に合ったというべきなのかもしれない。エドワードには分からなかった。吐息の通う音と暖かみが唇に感じ取れるほどに程近いところまで彼女の顔が近付く。
しかし、唇は触れなかった。
その代わりのように、ウィンリィの言葉が低く、唇の上に落ちてくる。
「おぼえておくわ」
それが、先ほどのエドワードの言葉に対する返答だと気付いたときには、エドワードは整備室のドアの外にいた。唇が触れる寸前、ウィンリィは突き放すようにエドワードを扉の外に押し出したのだ。
バタンと盛大に音がして、そのあとは、待合室に静寂が落ちるのみだった。声もなく、エドワードは閉まってしまった木製の扉を孔があくほどに見つめた。
(なんだ、それ)
おぼえておく? 何を?
エドワードは反芻する。自分は何のつもりで、「おぼえてろよ」などと言ったのか。
エドワードは左手の指先を、自分の口元に持っていく。与えられなかった唇に想って、眩暈がしていた。そして、辿るように蘇る、口の中に残っている味。指先にキスをした。何の考えもなく。舌先にのせた彼女の血と指先の味を思い出しそうになって、エドワードは焦った。
なぜだかひどく後ろめたかった。そして、同時に、とてつもない高揚を覚えていた。それが身の内を侵食していく。声をあげて、笑ってしまいたくなってくる。
(なにしてんだ、オレ)
唇に落とされた吐息と、低く囁かれた彼女の言葉。思い出すにつれて、立ち昇るこの感情。それを何と呼ぶのか。名前をつけるのが、怖かった。
(だめだろ)
何考えてる? とエドワードは思い直そうとする。それでも、視線は、扉を睨むように見つめていた。そこから、外せなかった。
(蓋をするんだ)
蓋をしたかった。見ない振りをしていた、蓋をしていたはずのそれが、溢れそうになっていて、エドワードは慄いていた。その感情を何と呼ぶのか、名前をつけてしまうのが、怖い。嫌ではなく、怖かった。慄きながら、それでも、扉から、視線が外せない。
ウィンリィ。そう、名前を呼んで、ドアノブに手をかけようとした時だった。
「……兄さん?」
呼び止められて、エドワードの動きは一瞬全て止まる。
振り返ると、アルフォンスがいる。
「なにしてるの?」
エドワードは声を失った。鎧姿の弟を見上げて、ゆるゆると身体から熱が引いていくのを自覚していく。
(蓋をする。蓋を、すればいい)
エドワードは喉を鳴らして息をひとつ呑んだ。見下ろしてくる弟の眼差しを真っ直ぐに見つめ返した。偽りたくなかった。しかし、既に、嘘は彼の知らないところで始まっていた。
「なんでもない」
アルフォンスは首をかしげる。
兄の表情はどこか硬い。自分を見上げてくる眼差しがどこか自分を見ていないようで、アルフォンスはいぶかしんだ。迷いを孕んだ金色の瞳は、緩やかに足元に視線を落とす。
ドアノブに掛けかけていた手を離すと、エドワードはそれを口元にやった。偽りを塗り重ねるのがひどく後ろめたくて、エドワードはぼそりと言った。
「……口ん中、ごろごろする」
「え?」
意味が分からない、とアルフォンスが首を傾げるのを横目でみて、エドワードはなんでもねぇよとまた繰り返した。ピナコを探さなければ、と止まりかけていた思考をゆるゆると動かす。しかし、一瞬だけ、エドワードは後ろ髪を引かれる思いで扉に目をやった。エドワードは見逃していなかった。あの瞬間、自分の頬に手を伸ばしてきた彼女の指先が、小刻みに震えていたことを。
しかし、ドアは沈黙を決め込んだまま、開く気配はなかった。
(中略)
首の後ろに、吐息を感じた気がした。
「待って」
低く押し殺したような彼女の声に、エドワードは背筋がぞくっとする。
「ここに、いて」
言いながら、ウィンリィはきゅっと彼の身体に両腕を回す。エドワードの手がドアノブから離れていくのを、後ろから彼の肩越しに確認して、ほっと息をついた。
「今だけでいいから、ここにいて」
「……。意味分かって言ってるのか、おまえ」
ウィンリィは背中にしがみついたまま、こっくりと頷く。
エドワードは黙ったまま、後ろを向いた。身体を入れ替えるようにして、ウィンリィと真正面から向かい合う。
視線の高さはほとんど同じだった。エドワードは真剣な表情で、ウィンリィを睨むように見つめてくる。
「分かってるわよ」
ウィンリィも負けじと彼を見つめ返す。
エドワードは静かに口を開いた。視線は逸らさずに、ウィンリィを見つめたままだ。
「朝も言ったけど」
「……」
「たぶん、傷つける。……たぶん、振り向いてる余裕が無い」
それでも……、と続けようとするエドワードの言葉に、ウィンリィは首を振る。
「あたしも朝言ったじゃない」
「……」
「何もいらない。責任とか要らないの。振り向かなくていい。……ただ、あんたにあたしがキスしたいだけ」
(指越しのキスなんか足りない)
彼が舐めた指先の傷を、唇を重ねるようにキスしても何の味もしなかった。自分の傷では意味が無い。
「あたしは傷つかないわ。言ったでしょ。傷を治すのがあたしの役目なんだって。怪我ばかりしてるあんたとあんたの機械鎧を直すのがあたしの役目なの。だから、あたしは傷なんてつかないわ」
ウィンリィはふわりと笑みを浮かべてさえみせた。
(だから、キスして? そうしたら、傷を舐めてあげる。……あんたのキズはキズナになるの。あたしとあんたを繋ぐ、絆なの)
エドワードは、ぎゅっと唇を引き結んだ。彼女は何も要らないと言う。一方的に、いつも与えられていることに気付く。それが本当は辛い。
「でも」
エドワードはウィンリィの身体に両腕を回す。ウィンリィは身を預けるように、彼の肩口に頬を寄せた。
「……守りたい」
エドワードは言いなおす。言えば、それが実現する気がした。まだ見えない未来に向かって、約束を施す。
「……守るから」
おまえを、と続ける言葉の代わりに、エドワードは回した腕に力をぎゅっと込める。ウィンリィは頷かなかった。ただ頬を寄せて、抱きしめられるがままになる。このまま壊れてもいいと思うほどに、強く強く抱きしめて欲しかった。今このときだけ、ここにいてほしい。離さないで欲しい。
(その絆を。そのつながりが欲しい)
だから、キズで贖うのだ。
ウィンリィは身体を離す。エドワードの両頬に手をあてた。
「キスして」
(そしたら、舐めてあげる。傷を)
エドワードは頬にあてられたウィンリィの片手をとる。そして、身を乗り出すようにして、顔を傾けた。ウィンリィが緩やかに瞳を閉じていくのを見ながら、自身もまた目をゆっくりと閉じる。そして、その甘いたおやかな唇に蓋をする。
*
(やっと触れた)
味があるわけではない。それでも、ウィンリィはそのかそけく触れた温もりのあまりの甘さに膝が崩れそうになる。
唇を離して、こつ、と額を彼の額に押し当てる。は、と息を軽くついて、程近いところで彼と視線を合わせた。
「エド」
「……」
金色の眼差しを浴びて、ウィンリィは震えた。それでも言わずにはおられなかった。額を押し当てて、彼の頬を捉えるようにしてしがみついて立っている。膝がガクガクと震えるのをなんとか耐えながら、ウィンリィは言った。
「すき」
「…………」
ウィンリィは一瞬瞳を伏せたあと、また真っ直ぐに彼の目を見つめる。
「すきなの」
言えば言うほど、心が濡れる。すきで満ちていく。もっと言いたくて、ウィンリィは唇を開く。しかし、叶わなかった。
ウィンリィが告白を続ける前に、エドワードの唇が彼女の言葉を塞ぐ。
「……も、言うな」
啄ばむように何度も彼女の唇を貪ったエドワードは、顔を離して、ようやくそれだけを言う。
(すげぇ拷問だ、これ)
抑えていたものが弾けていく。外れて、溢れてくる。それでも堪えるように、思いつめた表情でエドワードはウィンリィを見つめた。彼女の言葉は、拷問のようだった。甘く自分を絡めて堕としていく。
身体が自分のものではないような気がしていた。エドワードは慌てていた。せりあがる動悸につられるようにして、自分の顔に熱が昇っていくのを感じる。それを彼女に悟られるのが嫌で、エドワードはさらにウィンリィの唇を求めた。そうすれば、目を閉じてくれる彼女に、顔の赤い自分は見られない気がした。
「エ、ド……っ」
唇を啄ばまれる合間に、ウィンリィが困ったように声をあげる。身を引こうとしても、エドワードにがっちりと身体を掴まえられていて、逃げようがなかった。顔をひこうとすれば追いかけられる。顔の下から摘み取られるようにキスを施される。
ぎこちなくかわされるキスは徐々に巧みになっていく。まるで試すかのように、エドワードはウィンリィの唇を食んだり、舌を差し入れたり、舐めたりした。貪るようにキスを何度もかわして、ウィンリィは立っていられなくなる。
「まだだ」
崩れそうになるウィンリィの身体を抱えるようにして、エドワードは夢中でキスをする。
「してって言ったのは、おまえのほうだろ……?」
息を乱しながら、銀色の糸をひく唇を舐めた彼は、なおも顔を傾ける。
しがみつくように彼の背中に手を伸ばして、ウィンリィは彼のキスを受け止める。意識の最奥から甘く痺れて、霞がかかっていくようだった。そんな甘い口付けを何度となく交わす。
キスの応酬は何度となく続いて、休憩するように、ウィンリィはエドワードの首筋におもむろに抱きついた。抱きついた腕から彼の熱がじんわりと伝わる。それに眩暈を覚えながら、唇を彼の耳元に寄せた。
「すき」
だから、抱いて。
ただそれだけなのだ。何も考えていなかった。ただ欲しいだけ。エドワードは何も考える必要は無かった。自分も何も考えていないのだ。
(何もいらない。振り返らなくていい。ただ、前を見据えるあんたの背中をあたしは見送る。でも、今だけは)
エドワードがお返しのように、耳に唇を寄せてくる。息を吹きかけられるだけで身体に痺れが走る。身をくねらせながらエドワードにしがみつく。
(いまだけは、あたしだけ見てて)
ひどく身勝手なことを願っている。している。分かっていた。
それでも、止まらない。
息を乱しながら、エドワードが耳朶に舌を這わせてくる。ピアスをあけたウィンリィの耳に、お構いなしに口付け、舌で貪る。彼の舌と吐息と熱にうかされそうになりながら、ウィンリィは緩やかに息をあげていく。耳から首筋へ、舌先を移動させていくエドワードは、左手では彼女の胸に手を這わせ始めていた。ひどく恥ずかしかったが、ウィンリィは止めはしなかった。
「ん……んン……」
肩で息をしながら、ウィンリィはエドワードの舌先の愛撫を受けていた。エドワードはキスを続けながらゆっくりと歩を進める。首筋にキス痕をつけたあと、またウィンリィの唇を塞いだ。キスの合間に、ウィンリィに視線で促す。彼女の背中に腕を回したまま、ベッドのあるほうへゆっくりと移動していく。
「ん……ァ……」
唇を離してウィンリィをベッドの上に押し倒す。ぎしぎしと軽い悲鳴をあげて、ベッドのスプリングが軋んだ。揺れる視界の中央にエドワードを見留めて、ウィンリィは腕を伸ばす。切なげに息を乱しながらエドワードにせがむ。
エドワードは履いていたブーツを脱ぎ捨てると、ウィンリィの身体を横から抱きすくめる。彼女が首を仰け反らせるようにして、背後のエドワードに口付けをせがむと、応えるように唇を施す。キスを続けながら、エドワードの手はウィンリィの胸の膨らみをほっこりと包み始めていた。
どうすりゃいいんだ、という思考よりも先に、エドワードの身体は動いていた。何も考えずに、ただ彼女を求める。
黒いチューブトップの上から、丸い膨らみを左手で揉んでいく。形を確かめるように、包んだり揉んだりを繰り返して、そのうち、布地の下へと手を滑り込ませる。
「んん……」
ウィンリィが小さく身をよじって息を乱し始める。エドワードはキスをやめない。チューブトップの下に潜り込ませた指先は、彼女の膨らみの先端にたどりついていた。指の腹で刺激するようにそれを丸く撫で上げれば、ウィンリィは緩やかに息をあげていく。
ひとしきり胸を弄った彼は、おもむろに、左手をウィンリィの腹部に這わせた。ウィンリィは作業服の下にはチューブトップをつけているが、腹はむき出しのままだ。つるりと白く滑らかな肌を指先で撫でながら、エドワードの手はウィンリィの臍、そして、さらにその下へと伸びていく。
「エド……」
つなぎの下に手を差し入れられそうになっていて、初めてウィンリィが声をあげた。恥ずかしそうに睫を伏せるウィンリィの頬は、薄暗い橙色の灯りのしたでもそれと分かるほどに赤色に染め上がっている。
「ま……って……」
ウィンリィは困ったように、ベッド脇の灯りに視線を彷徨わせる。
「電気消して」
つなぎの下に手を差し入れたエドワードの答えは明快だった。ウィンリィの耳元に唇を寄せて、耳朶を食む。息を吹きかけるようにして、いやだ、と答えを下す。
「……はずかしい」
「だめだ」
ん、とウィンリィは息を詰めて目を閉じる。そんな彼女の様子を逐一見つめながら、エドワードは彼女の足の間に指を這わせていく。つなぎの下に差し入れられたエドワードの手が、もぞもぞと蠢いた。
「消したら、……おまえが見えないし」
「でも……」
言いかけて、ウィンリィの言葉は途中で詰まる。ぴく、と身体が魚のように細かに震えた。
目を閉じていても、エドワードの指が何をしているかウィンリィには全て分かっていた。彼はまだ下着の中にまで指を入れていない。しかし布越しに撫でてくる。触られるたびに身体が熱くなっていく。
「エドぉ……」
ウィンリィは泣きそうな表情でエドワードの顔を見上げようとするが、エドワードは指を動かしたまま、横から掻き抱いたウィンリィの耳元や首筋に口付けるのに忙しい。
「だいじょうぶ……」
蚊の泣くような声で名を呼ぶウィンリィを、エドワードは宥めるように唇にキスをする。そして口付けながら、ウィンリィの足の間に差し入れた指の動きをゆっくりと早めていく。
「んんんンッ……」
ウィンリィはきつく目を閉じて、エドワードのキスと、指先の愛撫を受ける。頭の中で映像が浮かぶようだった。エドワードの指が何をしているか。下着の上からの曖昧な愛撫は、徐々に激しくなっていく。指二本を使って、下着の上から恥ずかしいほどに敏感に感じる部分をくしゅくしゅと擦られる。ウィンリィは足を閉じようとするが、エドワードには敵わなかった。触られているところから緩やかに熱は身体中に浸透し、ウィンリィから力を抜いていく。
「気持ちいい?」
は、と息をつきながら唇を離すと、エドワードは息を乱しながらぼんやりと自分を見上げてくるウィンリィに問う。
「……うん」
ウィンリィは顔を赤く染めてそっぽを向くように小さく言い置いた。視線を合わせようとしないウィンリィの額にエドワードはひとつだけキスを落とすと、ウィンリィの下腹部から指を引き抜いた。そして、彼女の足を押し広げると、その間に身体を割り込むようにして、ウィンリィの身体の上にのしかかる。
ウィンリィの白い肢体の上に、橙がかったエドワードの影が掛かる。ウィンリィの真正面に膝たちになったエドワードは、彼女の胸を覆うチューブトップをおもむろに胸の下に引き下げた。
は、と息を吐きながら、エドワードは彼女の胸に顔を埋める。
「あ……」
外気に晒された胸の先端に、エドワードはおもむろに口付ける。舌先を伸ばして、形をえぐるように乳首の先端をなぞった。ちゅ、ちゅと音を立てながら交互に口に含む。
「ん……ん…ッ」
ウィンリィは身体をくねらせながら、両手をを口元に持っていく。声を出したくなくて、指先を唇にあてて、肩で息をする。
エドワードの唇はウィンリィの両の乳房の丸い稜線を辿ると、胸の間、腹部、臍と舌先を走らせていく。腹部に口付けながらつなぎを足から引き抜き、下着さえも取り去る。
「エド……エド……」
ウィンリィはせわしなく彼の名を呼んだ。しかし、エドワードは構わずに、彼女の足を押し広げる。
「や………」
初めてウィンリィが抵抗するような声をあげた。彼が何をするのか分からなくて、ウィンリィは動転する。
「エド……っ」
足を広げたウィンリィは、身体は横たえたままだったが、思わず上体を起こそうとする。しかし、間に合わなかった。突如施された刺激に、ウィンリィは身を仰け反らせる。
▲上へ戻る。
2.「今宵、月咲く庭で君と」より抜粋
オレは思わず顔が固まる。
「おま……壊したんじゃねぇだろな?」
「なんなら開けてみる?」
「……」
オレは一瞬考え込んだあと、いや、いい、と彼女の言葉を打ち消す。鎖を絡めた彼女の手に手を重ねるようにして包んだまま、もう一度キスをする。
月の光の下で、芝生の上に横たわった彼女は、金色の髪を波のようにうねらせていて、オレを下から見上げてくる青の眼差しや、白い頬、吐息を通わせるその唇まで、しっかりと見える。蒼い光さえも取り込んだその艶やかな眼差しに誘われるように、オレは彼女に何度も何度も口づけた。額に頬に、唇に。
空気を溶け合わせるようにして、息づく桜色の唇に蓋をして舌を絡ませば、ひそやかに横たわる闇の中で二人分の吐息が熱を帯びて大きくなっていく。
「エド……?」
唇から首筋、耳のうしろ、順番に口づけていくオレに、さすがにウィンリィは変に思ったのか、身をよじり始める。
「……ヤ……ちょ、と……」
ぎょっとしたように、ウィンリィが身を竦ませたが、オレは構わなかった。コートに覆われた胸を、右手で布地の上からさわりはじめる。感触は、もちろん無い。
「なに、する、気?」
「ナニする気」
鼻先を近づけあうようにして、彼女をまっすぐに見下ろす。月明かりの下でも、彼女の白い頬が、さっと朱を立ち昇らせる。オレは息ひとつ呑んで、恥らうように動揺を見せる彼女の挙動を見つめる。
「や……だ。……こんな、とこで」
ウィンリィはオレをおしのけようとするがオレにはかなわない。おまえこそ、とオレは囁く。
「こんなカッコで」
「……」
「ふらふら外に出て」
「…………」
「誰かに見られて欲しいの? おまえ?」
「……ぁ…っ」
やだ、とばかりに顔を赤らめたウィンリィが、オレの機械鎧の手を押さえようとするが、逆にオレは地面に彼女の手を押さえつけた。唇でコートの前をゆっくりと肌蹴させる。オレの目の前に現れるのは、白磁のようなすべらかな肌に、おびえるように光の下に晒された赤い果実が二つ。
「え……ど……」
「声。出すなよ?」
囁きながら、オレは舌先を尖らせて、肌に吸い付く。
「……ッ!」
ちゅる、と肌を舐める音は思いのほか大きく闇に響く。身を縮めるウィンリィの胸がわずかにはねた。椀を伏せたような丸い柔らかな乳房に、オレは顔を埋めるようにして舌を這わせた。形を露にさせる乳首を、ちゅ、と音を立てて交互に吸う。
曲線を描く両の乳房の稜線に痕をつけながら、オレは彼女の胸の谷間から腹部へと舌だけを触れ走らせながら愛撫していく。吸い付くような張りのある肌は、幾らでも口づけていたかった。彼女がいちいち身体を震わせて反応してくるので、それも可愛い。両手を繋いだまま、顔だけを彼女の腹部へ這わせる。わき腹の辺りを舌で撫でると、くすぐったそうにウィンリィは声をあげた。
「バカ」
オレは咎めるように顔をあげて、彼女を軽く睨むフリをする。
「だって」
ウィンリィは困ったように唇を尖らせた。
「こんなとこじゃ……やだ」
少しばかり息を乱した彼女は、濡れたような青の眼差しを差し向けて、オレにやめるように訴える。月明かりの下で、潤いを含んだ瞳も、珊瑚色に光を弾く唇も、桜色に蒸気した頬も、壮絶に可愛い。
ああどうしてこんなに夢中になってしまうのか。理由が分からない。理性で処理する前に、本能で手一杯になる。
口には出さないけれど。オレはこっそり息を呑む。身体を重ねた時は電気をつけていなかった。彼女が嫌がったからだ。つけていればよかったな、と少し後悔する。次からは絶対に消してやらねぇ。
▲上へ戻る。
3.「そして、祈るように目を閉じた。」より抜粋
彼の動作を想像する。足を広げ、屹立したそれを自分の中に入れてくれればいい。それだけで、きっと全て忘れる。
しかし、身構えていたウィンリィに、それは与えられない。
「ん……んぁ……ッ?」
違う刺激にウィンリィは身体を撥ねた。驚いて目を見開く。視界の真ん中に彼が居た。しかし、彼のものは自分の中には入ってこない。なんで、と問う間もなく、ウィンリィは身体をよじる。
「や……だぁ……」
半泣きになりながら、ウィンリィは嫌々するように首を振った。しかし、エドワードは止めようとしなかった。くちゅくちゅとイヤらしい音が耳に届いたような気がした。ウィンリィは小刻みに身体を震わせる。彼の動きに合わせて、腰が震えた。彼は、屹立したそれを、ウィンリィの尖った陰核に押し当てたのだ。既に先走りの出ているそれを、彼女の赤く熟れた鳥の嘴に押し当て、塗りたくるように丸くこすり付けて蹂躙する。
「や、やだ……エド……」
息を乱しながら、ウィンリィは鳴く。恥ずかしさでどうにかなりそうだった。エドワードはわずかに息を乱すのみで、ウィンリィの反応を面白がるように見ながら、こすり付けるのをやめようとしない。ちょっとした悪戯のつもりだったのだが、エドワードはあまりに扇情的な反応を示す彼女に、思わず夢中になってしまう。
「あ……あンぅ…ッ…」
くちゅくちゅと粘着質の音を立てながら、エドワードは執拗に愛撫を繰り返した。ウィンリィの息は乱れに乱れて、軽く達してしまう。
「ば、か……ッ」
顔を赤くさせ、肩で息をしながら、ウィンリィは悪態をついた。エドワードは息をついて、ウィンリィに唇に軽くキスを落とす。彼女は強情だ。
「オレも、はやくしたいんだけど」
正直、我慢も限界に近かったのだが、やはり知りたくて、エドワードは悪戯をやめない。
はぁはぁと息を乱し、ウィンリィは涙目になりながらエドワードを軽く睨んだ。彼は強情だ。諦めない気がした。
折れたのはウィンリィのほうだった。
(中略)
疲れ果てて失った意識を取り戻したとき、しかしまだ夜は明けていなかった。
身体に残る余韻をもてあましながら、エドワードはうっすらと目を開く。抱きとめるようにして彼女の身体に身体を密着させて眠りについたはずなのに、腕の中にそれが無いと気付いて、ひやりとした。しかし、巡らせた視界に、うっすらと見慣れたシルエットを捉えて、エドワードは力が抜ける。
ウィンリィはエドワードの隣で上半身を起こしていた。乱れた髪をそのまま背中まで垂らしている。服を着ていない彼女の身体には、赤すぎる跡がいくつかついていて、白い月明かりの下で、それはまるで花びらでも散らしたように見えた。
ウィンリィは泣いていなかった。エドワードが目を覚ましたことを、彼女はまだ気付いていないようだった。エドワードは息を殺しながら、彼女を下から見上げる。顔はよく見えない。俯き加減の彼女は、おもむろに、両の手をあわせる。音は立てなかった。しかし、自分の真似をしているのだと、行為の前の彼女の言葉をエドワードは思い出していた。手と手を合わせて、彼女は指先を唇にひたりとあてているようだった。そのままじっと動かない。彼女がどうしてそれをするのか、エドワードは分からなかった。意味があるとは思えなかった。しかし、無言で手を合わせる彼女を見ながら、エドワードの胸のうちには、ひとつの形容がぴたりと落ちてくる。
(きれい、だ)
月の光が、低く窓から零れている。夜明けは近い。色味を薄くした群青の夜明かりを一身に浴びて、ウィンリィは手を合わせている。表情は見えなくても、その姿は、きれい、という形容がぴったりだった。それは、願いの姿に似ている。
ウィンリィは目を丸くした。
「エド……?」
おもむろに、横たわっていた彼の影が動き出して、ウィンリィはぎくりとする。起きてたの、とウィンリィが言いかける前に、身体を引き寄せられた。ぐいっと抱きとめられる。
「あ」
ウィンリィはなおも目を丸く見開く。エドワードはウィンリィを包むように、背後から身体をぴたりと寄せてくる。
そして、後ろから、彼女の手に手を合わせたのだ。
「エド……」
ウィンリィは感情の読み取れない淡々とした声で、小さく彼の名を呼んだ。胸の前に両の手を合わせる。その上に、彼の手が重なる。左手には彼の生身の左手が、そして、右手の上には、彼の機械の手が。ほっこりとした暖かさと、ひやりと刺すような冷たさが、同時に手の中に生まれる。
「分かってるわよ。……何も、起きないって」
言われる前に、自嘲的にウィンリィはそう言葉を漏らした。そう、分かっているのだ。自分は彼にはなれない。笑われたくなくて、先回りするように言い訳する。しかし、エドワードの言葉は、ウィンリィが予想していたものとは全く違うものだった。
「なんでも、造れたらいいのにな」
エドワードの声が小さく耳元に響く。彼の言葉に、力は無い。何かを諭すわけでも、何かに言い訳するわけでもなく、ただただ淡々とした口調だった。
エドワードは、ちりりと胸の痛みをひとつ覚える。何でも造れる。そう過信した時代があった。何も知らなかった幼い頃、犯してしまった禁忌があった。絶望の淵から這い上がる術を、胸の中の彼女が与えてくれた。
「オレがこれを使えるのは、おまえのお陰だ」
彼はぽつんと小さく呟いた。
(知ってるわ)
しかし、ウィンリィは頷かなかった。錬金術のことはよくは分からない。しかし、自分の造った右腕が、彼に錬金術を使わせる。そして、彼を、あの戦場に向かわせる。それを、身をもって知ったのだ。
(あたしが与えたものが、あたしが欲しいものを、奪っていく)
それを悟ったウィンリィを捉え、離さない感情の名は、恐怖だった。自分の機械鎧が彼の役に立つ、という喜びといつも背中合わせに存在する畏怖だった。だから、ウィンリィは謝りたかったのだ。
(あんたを、サポートするって、言ったのに)
同時に、欲する自分を、許して欲しい。
願いに相反するように、触れられた手のぬくもりと冷たさにじんわりと心が濡れる。それを、ウィンリィは否定できない。
「これがあるから、前に進める」
しかし、ウィンリィの気持ちとは裏腹に、エドワードは言葉を続ける。
「だから、心配するな」
▲上へ戻る。
4.「未完成な赤色」より抜粋
まどろみの中、揺れる赤を見る。
夢の中で、いつも見えるその色。それは彼の色だった。
目を醒ますと、視界が小さく上下に揺れている。彼の胸の上だとすぐに分かった。頬をあてて、上下する彼の呼吸を全身で受け止める。身体の中に、まだ彼がいた。疼く胎内に眩暈を覚えながら、ウィンリィは小さく身体を起こす。
「気が済んだか」
低い声がする。ウィンリィは肩にハニィブロンドを滑り落としながら、身体の下に組み敷いた格好の彼を見下ろした。
黒いシャツさえも脱いでいない彼は、赤いコートを下敷きにして床の上に寝転がってる。
結局、エドワードは一度もウィンリィの手を離さなかった。少なくとも、甘い快感に混濁する記憶の限りで、ウィンリィはそう思っていた。
横たわる彼の黒いシャツは乱れている。鎖骨の辺りに、ウィンリィは視線を這わす。そこに匂い立つように花開く、キスの痕があった。
「エドは」
ウィンリィは握られた左手とは逆の右手を軽く床について、エドワードの顔を覗きこむ。
「気が、済むの?」
離れたところから、ぽっかりと孔があいていく。それを何かで満たしたくて、焦がれていた。満たしても満たしても、まだ足りない。
ウィンリィの眼差しを真っ直ぐに受け止めながら、エドワードは生身の左手を彼女の頬に添えた。濡れた頬をゆっくりと擦るように撫でる。触れたところにほっこりと熱が伝わる。しかし、絶えず離せなかった右腕には、熱は伝わらない。そこからぽっかりと孔が空いていくようだった。埋められない隙間をなんとか埋めたくて心がいつも喘いでいる。
(いつか)
さすってもさすっても濡れる彼女の頬を撫でながら、エドワードは刺すような胸の痛みに眉をしかめた。
(いつか、完全な身体になって、完全におまえを感じたい)
身体全部を使って、感じたい。だから。
「……まだ、足りねぇ」
頬を指先で上下に擦りながら、エドワードは目を細める。
「いつか、腕と足を取り戻したら」
「…………」
頬を撫でる指先を彼女の唇に軽く添える。ふにゅっと柔らかい感触が親指に落ちる。
「満足するかもしれねぇけど」
ごめんな、という言葉を、彼は小さく唇にのせる。
ウィンリィは首を振った。暗澹とした想いで彼の言葉を受け止めながら、ウィンリィはおもむろに身体を倒す。
「ウィンリィ……?」
謝らないで、と彼女は小さく呟いた。
(謝らなければならないのは、むしろあたしのほうなのに)
ウィンリィは彼の整備師で、だから、自分が造った腕で以って自分を触る彼が、触れ方を分からないというのなら、教えるのも自分の役目だと思ったのだ。彼が自分を必要とする。それが嬉しかった。だから、彼が謝ると、後ろめたくなる。
(未完成なあんたを、すきと思って、ごめんね)
機械鎧をつけている限り、エドワードは必要としてくれる。それがただひたすらに嬉しい。そして、後ろめたい。
▲上へ戻る。
5.「微熱ゲーム2」より抜粋
「どうして?」
ほらきた、とエドワードは小さく息を呑む。逃げられない。誤魔化せない。感じたくないと思っていても、身体はやっぱり感じてしまうのだ。だから、誤魔化せない。
「夢を、見るんだ」
ウィンリィは小さく目を見開いた。手繰るように二人の視線は同じところで重なる。胸がどうしようもなく高鳴るのを感じながら、ウィンリィは彼の言葉を待つ。
「最低最悪な、夢なんだ」
言いながら、エドワードはウィンリィの両手に自分の両手を繋ぐ。そして、そのまま、それを壁際へと押し付ける。まるで磔にでもされたような格好で、ウィンリィは両腕を拘束されたままエドワードを見返した。
「どんな、夢?」
エドワードはまたひとつ、小さく息を呑む。一瞬、彼の金色の両目が遠い何かを見たような気がして、ウィンリィは目を見張った。一瞬だけ彼の太陽色の目を翳った「何か」がなんなのか知りたかった。
「……いえない」
ウィンリィの顔に失望の色が宿る。それを、力なく眺めながらエドワードは苦いものでも飲んだように表情を歪ませた。
(おまえは、「ここ」に来なくていい。来たら、駄目だ)
だから、知らなくていい。何も知らないまま、そのままでいればいい。
壁に押し付けた彼女の両手を強く握りなおす。彼女の右手に自分の左手を、そして、彼女の左手に、自分の機械の手を重ねて、力を込める。
「忘れたいんだ」
それは嘘だと、エドワード自身よく分かっていた。忘れたいんじゃない。思い出したくないだけだ。忘れることなんて絶対に出来ないのだから。夢を忘れることも、彼女と共有した快楽を忘れることも、決して出来ないのだ。感じない振りをしても身体はどうしても反応する。誰とも知れない何かに、エドワードは必死で言い訳を繰り返している気がしていた。誤魔化し続けている気がした。感じてないと誤魔化そうとして、あの罪の匂いがする夢に言い訳している。……あるいは、身体の無い弟に対して。
「おまえに忘れさせたいんじゃない。……オレが、忘れたい、んだ」
だから、抱く。言い訳を繰り返すように。
指を絡ませて、エドワードはウィンリィの両腕を押さえつけたまま、顔を傾ける。ねっとりと唇を重ねた。
「忘れさせてくれよ」
唇を離しながら、低い声で囁く。そして、片手をウィンリィの胸にそろりと這わせる。丸い果実のようなその膨らみの重さを手のひらに確かめるように持ち上げて、ゆっくりと揉みしだく。
胸を隠そうと垂れてくる彼女のシャツが邪魔で、エドワードはそれをさらに上へとたくしあげる。ウィンリィに万歳をするような格好をとらせると、エドワードはそのシャツを脱がせようとする。しかし、ウィンリィの頭をシャツから出させたあと、エドワードは、手首のところでその裾をきゅっと縛った。
「エ、ド……?」
両腕を頭の上に乗せたような格好のまま縛られたウィンリィは、目を丸くする。
「な、に、する、気……?」
エドワードは無言で、その両手首を縛ったシャツを、おもむろにドアノブに引っ掛ける。鍵のかかったドアは、ぎしぎしと小さく軋んだが、それでもウィンリィの体重を受け止める。
▲上へ戻る。
……続きは本文で。
![]()